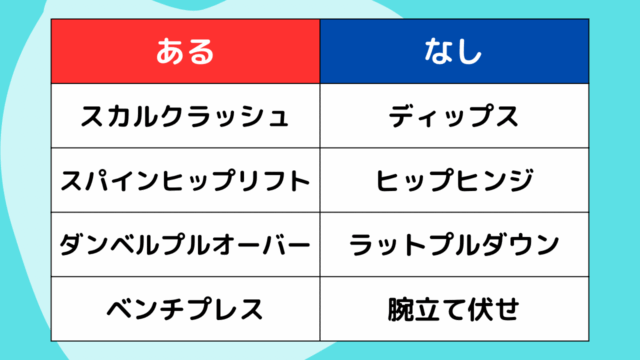運動をすると頭が良くなる?科学が示す驚きの関係 - physica
一見、運動能力と学力は関係ないように思えますが、実は脳科学や教育学の分野でこのテーマはしっかり研究されています。
運動と脳の関係は科学的に証明されている
カリフォルニア州で行われた2004年の大規模調査では、体力と学業成績の関係に注目しました。
この研究は、約95万人の児童・生徒を対象に「体力テスト(筋力、柔軟性、有酸素能力など)」と「学力テスト(英語、数学)」の相関を分析したものです。
その結果、以下の傾向が明らかになりました。
・男女問わず、体力が高いグループの学力テストの平均点は、低いグループに比べて高い。
・体力テストの成績が高い生徒ほど、学力テストの成績も高い傾向がある。
・その中でも特に有酸素運動能力(心肺持久力)と強い相関性が認められる。
これは、脳の血流改善やホルモン分泌による集中力アップなど、運動が学習に良い影響を与えるとする先行研究を裏付けるものと考えられています。
なぜ運動で頭が良くなるのか?

運動が学習に良い影響を与えると考えられている理由は、主に以下の3つです。
● 脳の血流がアップ
運動すると心拍数が上がり、血流が全身に巡ります。もちろん脳にも酸素と栄養がたっぷり届くため、神経細胞の働きが活発になります。
● 脳の成長因子「BDNF」が増える
BDNF(脳由来神経栄養因子)は、脳の神経細胞を修復・成長させる物質。ジョギングや筋トレをすると、このBDNFが分泌され、記憶力や学習能力の向上に寄与します。
● ストレスホルモンが減り、集中力が高まる
運動はストレスホルモンのコルチゾールを減らし、同時に幸福ホルモンのセロトニンやドーパミンを増やします。その結果、集中力やモチベーションがアップします。
運動は認知症予防にも

運動が良い影響を与えるのは子どもの学力だけではありません。
多くの観察研究において、定期的な身体活動は認知症やアルツハイマー型認知症の発症率の低下と関連すると報告されていること、さらに認知症のない高齢者や軽度認知障害を呈する高齢者に対する身体活動の介入試験では、認知機能低下を抑制したという報告から、運動は認知症予防にも効果的であることが分かっています。
脳を使うには、まず体を動かすこと
カリフォルニア州の調査からわかったことは、体力のある子どもは、そうでない子どもよりも学力が高い傾向があるということ。
もちろん、これは「因果関係」ではなく「相関関係」なので、運動が直接学力を上げると断定はできません。勤勉な生徒は運動と勉強を共に頑張る傾向があるのかもしれませんし、学力には家庭環境も影響しますが、運動が脳の働きを助けるのは科学的にも納得できます。
「脳を使うには、まず体を動かすこと」。これは学生だけでなく、大人にも当てはまりそうです。
参考:A Study of the Relationship Between Physical Fitness and Academic Achievement in California Using 2004 Test Results
参考:日本神経学会『認知症疾患診療ガイドライン2017』
この記事のライター
physica編集部
楽しくて役に立つフィットネス情報をお届けしています。