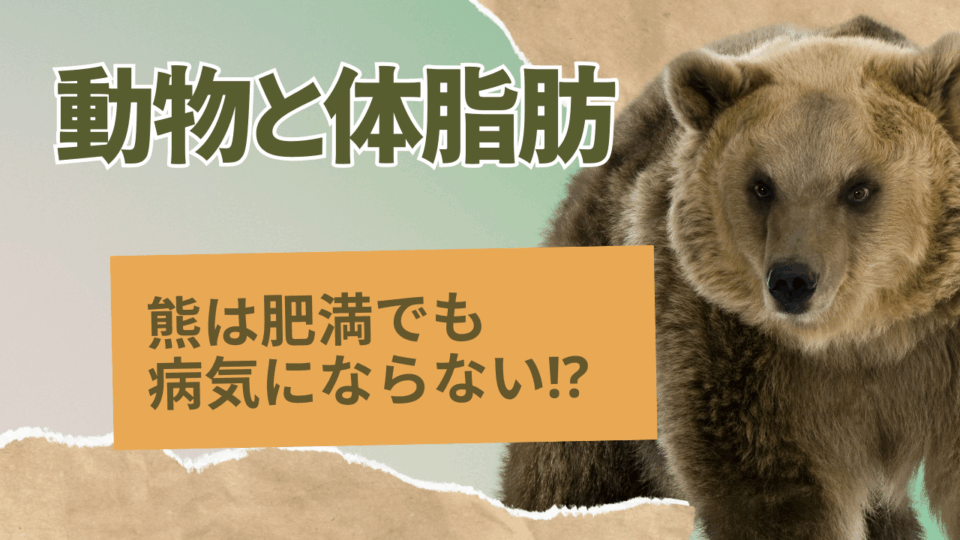
動物と体脂肪:クマは肥満でも病気にならない!? - physica
体脂肪と聞くと「ダイエットの敵」というイメージがありますが、動物にとって脂肪は生命を守る重要な体の組織です。
興味深いのは、動物の種類によってその量や付き方が様々あること。
今回は、動物の体脂肪がどんな特徴があってどんな役割を果たしているのか、人間と比べながら見ていきたいと思います。
体脂肪の役割が特徴的な動物たち
1. クマは肥満でも病気にならない!?

クマは冬眠に備えて、秋には大量の食物を摂り、体重が2倍から3倍にまで増加します。この時期の体脂肪率は30〜40%に達することが多く、ホッキョクグマではさらに高く、50%にもなることがあります。
人間がこのレベルの体脂肪率になると、脂肪肝や高脂血症、糖尿病などの生活習慣病を発症するリスクが高まりますが、クマはこれらの病気にかかりません。これは、クマの体内に脂肪を効率的に蓄積し、利用するための特殊な生理・代謝機構が備わっているためと考えられています。研究により、冬眠中の血糖値は活動期と同程度に維持されており、代謝障害が生じないことが明らかになっています。
また、メスのクマは体脂肪率が20%以上ないと妊娠できないとされており、体脂肪の蓄積は繁殖にも重要な役割を果たしています。
2. アザラシの多機能的フォルム

アザラシの体脂肪は、極寒の海で生き抜くための最も重要な適応の一つです。その特徴は、主に以下の点に集約されます。
アザラシの体脂肪率は、種類や時期にもよりますが、50%以上に達することが一般的です。
アザラシの体脂肪は、内臓脂肪ではなく、皮膚の下に分厚い層として蓄積されます。この皮下脂肪は、体を丸ごと覆う天然の断熱材のような役割を果たし、冷たい海水の中でも体温を効率的に保ちます。アザラシの毛は短く、保温効果はほとんどないため、この皮下脂肪が体温維持の大部分を担っています。
また、アザラシは、陸上で過ごす時間や、餌が少ない時期に備えて、体脂肪をエネルギー源として利用します。特に、繁殖期には陸上や氷の上で絶食する期間があるため、その間に必要なエネルギーを体脂肪から供給します。
さらに、分厚い脂肪層はアザラシの体を水中で浮きやすくすると同時に、アザラシの体を水の抵抗を受けにくいなめらかな流線形に保ち、水中での遊泳をスムーズにします。これにより、潜水や水中での移動を効率的に行うことができます。
3. ラクダの巧妙な体温調節システム

ラクダのコブは脂肪でできていて、ラクダが長期間にわたって食物を摂取できない場合に備えたエネルギー貯蔵庫としての役割を果たしています。
また、ラクダは脂肪をコブに集中させているため、体全体に脂肪が分散していません。これにより、体表面からの熱放散を妨げることがなく、暑い砂漠の環境でも体温が上がりすぎるのを防ぐことができます。もし体全体に脂肪を蓄えていると、アザラシのように熱を逃がしにくくなり、オーバーヒートしてしまうリスクが高まります。
コウモリの褐色脂肪細胞

多くのコウモリは冬眠する動物です。冬眠中は餌を食べることができないため、秋のうちに脂肪を蓄え、冬眠中のエネルギー源として利用します。冬眠に入る前の体脂肪率は30〜40%に達することもあると言われています。
また、コウモリの脂肪組織には褐色脂肪細胞が発達しています。これは、冬眠から目覚める際に、効率的に熱を産生するために重要な役割を果たします。褐色脂肪細胞は、一般的な脂肪細胞(白色脂肪細胞)と比べて、多くの脂肪滴とミトコンドリアを含んでいるのが特徴です。
チーターのアスリート体型

チーターは、陸上動物の中でもトップクラスに体脂肪率が低いことで知られています。その体脂肪率は、一般的に4〜5%と非常に低く、これはアスリートとして最高のパフォーマンスを維持するのに適した値です。この低さは、最高時速110kmに達する短距離走に特化した体型を維持するために不可欠で、体脂肪が少ないことで体の重さを最小限に抑え、素早い加速と敏捷な動きを可能にしています。
また、チーターは一瞬のスピードで獲物を仕留めますが、狩猟の成功率は決して高くありません。また、獲物を仕留めた後も、ライオンやハイエナといった大型の捕食動物に獲物を奪われることが頻繁にあります。そのため、常に次の狩りに備えて、無駄な脂肪をつけないよう体が適応しています。
人間の体脂肪

人間の平均体脂肪率は、男性15%、女性25%。人間にとっても体脂肪は、エネルギーの貯蔵や体温の保持、ホルモンの分泌など、生きるために重要な役割を持っています。
しかし他の動物と比べると、その依存度は低めです。私たちが暮らす社会では、体脂肪がなければ越えられない季節も捕まえられない獲物もいません。
野生動物は生存戦略として脂肪を蓄えるのに対して、人間の場合は主に食事の不規則さやエネルギーの余剰で増えます。
必要だから、こそにある。
動物にとって脂肪はただの「余分な重り」ではありません。
寒さをしのぐため、食糧不足に備えるため、さらには泳ぐために使われるなど、その役割は多様です。人間にとっても脂肪は必要不可欠ですが、過不足ないのがちょうどいいです。自然界の動物たちの工夫を知ると、脂肪を見る目がちょっと変わるかもしれません。
この記事のライター
physica編集部
楽しくて役に立つフィットネス情報をお届けしています。

