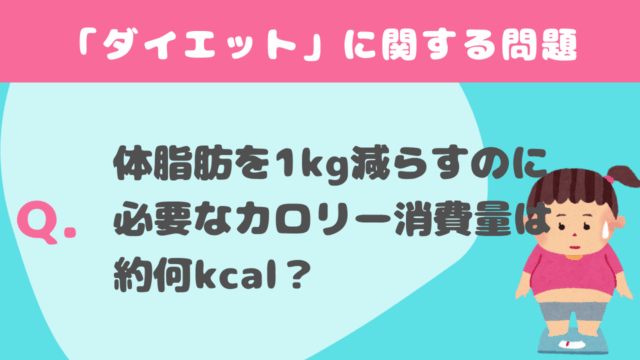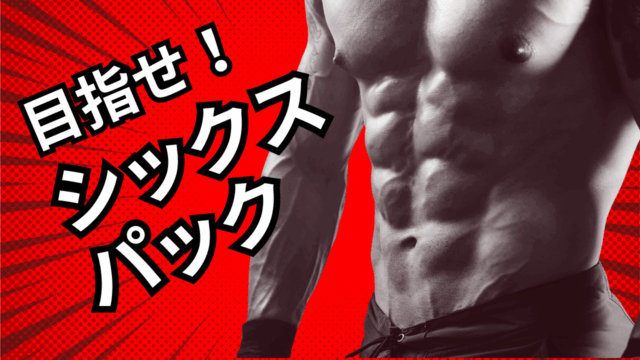映画で観たトレーニング考察!アレどんな効果?#2『ロッキー』編 - physica
こんにちは、フィジカ編集部です。
主演のシルヴェスタ・スタローンを一躍スターダムに押し上げた映画『ロッキー(1976年)』は、言わずと知れたボクシング映画の金字塔。
今回は、ロッキーが映画内で行っていたトレーニングの数々を、現代のトレーニング理論から分析し、どんな効果があるのかを考察していきます!
フィラデルフィアのしがないチンピラボクサー、ロッキー・バルボアが、まさかの世界チャンピオンに挑むという壮大なアメリカンドリームを描いたボクシング映画。トレーニングシーンで流れる「ロッキーのテーマ」(Gonna Fly Now)はあまりにも有名。
『ロッキー』のトレーニング
トレーニング①:ダンベルを持ってランニング

チャートフ=ウィンクラー・プロダクションズ/ユナイテッド・アーティスツ
映画の描写:
両手に軽めのダンベルを持ち、時折ジャブのようなパンチを打ちながらランニング。
現実的な効果:
実際、ダンベルを持ちながら走っている人は時々見かけます。ダンベルを持つことで振った腕には遠心力が働き、腕や肩まわりの筋肉には引き伸ばされるような負荷が加わります。また、シンプルにダンベルの重さの分だけ足腰への負荷も強まります。
ランニングのトレーニングとして見ると、(ダンベルが適度な重さであれば)腕振りの意識付けになったり、脚力の強化に繋がるとされており、日本で多くのトップランナーを育成した故・小出義雄監督も「フォームの左右バランスを矯正する目的で」一部の選手にこのトレーニングを指導していたようです。
ただ、ロッキーはランナーではなくボクサー。どちらかと言うと、ボクシングに必要な肩まわりの筋持久力を養う意味が大きかったのではないかと推測されます。
トレーニング②:片手腕立て伏せ

チャートフ=ウィンクラー・プロダクションズ/ユナイテッド・アーティスツ
映画の描写:
コーチや親友に見守られながら、左右交互に片手で腕立て伏せをするロッキー。
現実的な効果:
自重トレの王道「腕立て伏せ」ですが、片手で行う腕立て伏せは、両手で行うそれとは全くの別物。
大胸筋や三角筋、上腕三頭筋といった腕立て伏せに使われる筋肉の負荷が倍増するのはもちろんのこと…
重心が体の中央から外れることで、体には(トーソ・ローテーションマシンのような)捻れる力が常に加わり、体幹や脚の筋力強化にも効果絶大!
トレーニング③:市場での牛肉打ち

チャートフ=ウィンクラー・プロダクションズ/ユナイテッド・アーティスツ
映画の描写:
冷凍庫の中、吊るされた牛の枝肉を拳で叩き続けるロッキー。
現実的な効果:
これはサンドバッグ打ちに似た打撃練習になります。対象物に対してインパクトを加えることで、打撃時のフォームや力の伝え方を体得でき、打ち続けることでスタミナが鍛えられる要素もあります。
ただし、対象は「凍った」巨大な肉の塊。サンドバッグよりも硬く、拳を痛めやすいので現実でこれをやるボクサーはまずいないでしょう。
トレーニング④:石段ダッシュ(フィラデルフィア美術館までのランニング)

チャートフ=ウィンクラー・プロダクションズ/ユナイテッド・アーティスツ
映画の描写:
ロッキーが朝焼けの中、フィラデルフィアの街を走り抜け、石段を駆け上がる名シーン。
現実的な効果:
ランニング+ラストスパートの階段ダッシュは有酸素+筋持久系の最強コンボ。 これを日課にするだけで、心肺持久力と筋持久力は相当鍛えられるでしょう。
また、劇中ではゴール直前のメンタルの高揚、ゴールした際の達成感や自己肯定感が見受けられます。
総評:ロッキー式トレーニングは「心を鍛える筋トレ」でもある
『ロッキー』のトレーニングは、必ずしも科学的に最適とは言えない部分もあります。しかし、飢えた虎のような目でそのトレーニングに打ち込むロッキーの姿は観る人を熱くさせ、頭ではなく心で応援させてしまいます。
これまでロッキーはどれだけ多くの人に勇気とやる気を与えてきたことでしょうか。
この映画が教えてくれまのは、トレーニングの内容そのものより、トレーニングに対する真摯な姿勢とモチベーションの大切さのような気がします。
この記事のライター
physica編集部
楽しくて役に立つフィットネス情報をお届けしています。