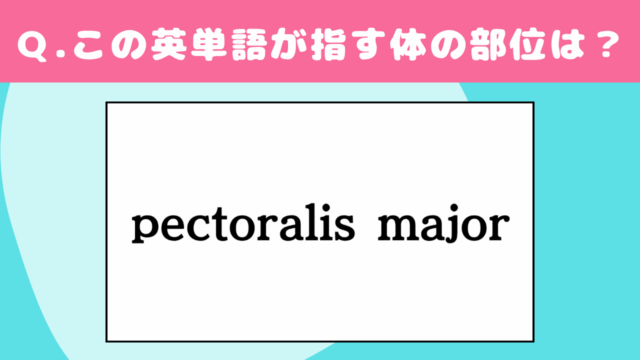【温故知新】いつからあった?日本のフィットネス - physica
こんにちは、フィジカ編集部です。
今日のテーマは――「日本におけるフィットネスの歴史」。
「フィットネス」と聞くと、筋トレやヨガ、ジムでのランニングマシンなどを思い浮かべる方が多いかもしれません。でも実は、日本人は何百年も前から、独自の形でフィットネスを育んできています。
今日はそんな日本のフィットネス変遷を見ていきましょう!
1. 古代〜中世:和製ミリタリーフィットネス
古代〜中世のフィットネスは、戦(いくさ)の中にありました。

・古代の相撲や弓術:宮中儀式や神事の一部として行われており、当時から身体の鍛錬が重視されていました。
・平安〜戦国時代:武士たちは、剣術・柔術・槍術などを通じて体と心を鍛える。これが現代の「武道」の始まりです。
この時代のフィットネスは、主に武士たちによる「戦いのための技術訓練」。生きるため、勝つために、戦いに自身を適応(フィット)させることが必要でした。
2. 江戸時代:生活の中のナチュラルフィットネス
江戸時代になると大規模な戦も少なくなり、武士はもちろん、庶民も体を使った労働に勤しむ日々を送っていました。

・徒歩移動・荷運び・掃除・水くみなど、日常がトレーニング。
・武士たちは道場で武道を続け、精神と体を同時に鍛える。
・1712年(正徳2年)、儒学者・貝原益軒が『養生訓』の中で「適度な運動が健康に良い」と提唱。現代にも通じる内容です。
運動が健康に良いという医学的な根拠や科学的なトレーニングこそまだありませんが、生活そのものが自然なフィットネスになっていました。
3. 明治〜昭和前期:体育という概念の登場
明治維新を境に、西洋の文化が急速に導入され、フィットネスの形も変化していきます。

・学校教育に「体育」が導入され、運動が“国民の義務”に。
・軍隊では体操や行軍訓練が徹底され、体力作りが国家的課題に。
・1928年(昭和2年)にはラジオ体操がスタート。日本独自の集団フィットネス習慣です。
この時代のフィットネスは、富国強兵の政策に基づいた国民を強くするための「鍛錬」。今なお続く習慣もありますが、現代のフィットネスとは根本が違います。
4. 戦後〜昭和後期:スポーツと娯楽の融合
敗戦後、日本は「スポーツを楽しむ」文化を取り入れていきます。

・東京オリンピック(1964年)を機に、国民的なスポーツブームが到来。
・この頃から、民間のスポーツクラブやスイミングスクールが広がり始めます。
・エアロビクスやジャズダンスなど、アメリカのフィットネス文化が日本に上陸。
・国内でも運動と健康に関する学術的な研究が進められます。
フィットネスが「鍛錬」から「健康のためのライフスタイル」へと変化。まさに日本の近代フィットネスの礎を築いた時代と呼べるでしょう。
5. 平成以降:フィットネスの多様化と個人化
1990年代以降、スポーツジム、パーソナルトレーニング、ヨガ、ピラティスなどが一般化。

・健康志向・ボディメイク・ダイエットなど、目的も多様に。
・スマホアプリや動画配信による「自宅フィットネス」も急成長。
・特に2020年以降のコロナ禍では、オンライン・フィットネスが爆発的に普及。
ライフスタイルとしてのフィットネスが正統進化。「いつでも、どこでも、自分のペース」で運動する時代へ。
6. これからのフィットネス:テクノロジー × 伝統文化
そして今、日本のフィットネスは新たな進化を迎えようとしています。

・VR・AIトレーニング:仮想空間での運動や、AIが指導してくれるトレーナーアプリの普及。
・和文化フィットネス:剣道、能、和太鼓など、伝統芸能とエクササイズの融合。
・高齢者フィットネス:さらなる高齢社会を迎える日本では、介護予防・筋力維持に特化した安全なトレーニングの需要拡大。
フィットネスも「個性・年齢・趣味」に合わせてカスタマイズされる時代に。
フィットネスのかたちは時代とともに変わる
フィットネスとは「健康の維持や向上のために行う運動」のことですが、本質的には「何かを行うのに適した状態にする」という意味も持っています。
そういう意味では、かつては戦うための鍛錬だったフィットネスも、今や人生を豊かにするための手段へと進化しました。
これからはフィットネスも多様性の時代です。また、日本においては少子高齢化という問題も無視できません。
過去から学び、未来へつなぐ――それもまた、フィットネスの在り方なのかもしれませんね。
この記事のライター
physica編集部
楽しくて役に立つフィットネス情報をお届けしています。