
江戸患いとは?〜江戸っ子の食生活と脚気の歴史〜 - physica
こんにちは、フィジカ編集部です。
皆さんは「江戸患い(えどわずらい)」という言葉を聞いたことはありますか?
これは江戸時代に流行した病気で、いわゆる「脚気(かっけ)」のことです。
今回は、かつて多くの人を悩ませた「脚気」と当時の日本に何が起きていたのか、歴史背景とあわせてご紹介します。
ビタミンB1欠乏症のこと。その名の通りビタミンB1の欠乏によって引き起こされる病気です。主な症状は、手足のしびれやむくみ、筋力低下、さらには心不全を引き起こして命を落とすこともあります。
なぜ"江戸"で流行したのか?
江戸患いの"江戸"は時代としての江戸ではなく、都市としての江戸です。
当時の日本人の主食といえば、麦や玄米が一般的でしたが、「将軍のお膝元」である江戸には年貢のお米が全国から集まってくるため、精米の技術も流通のシステムも発達していて、よほど貧しくない限り庶民でも白米を食べることができていました。
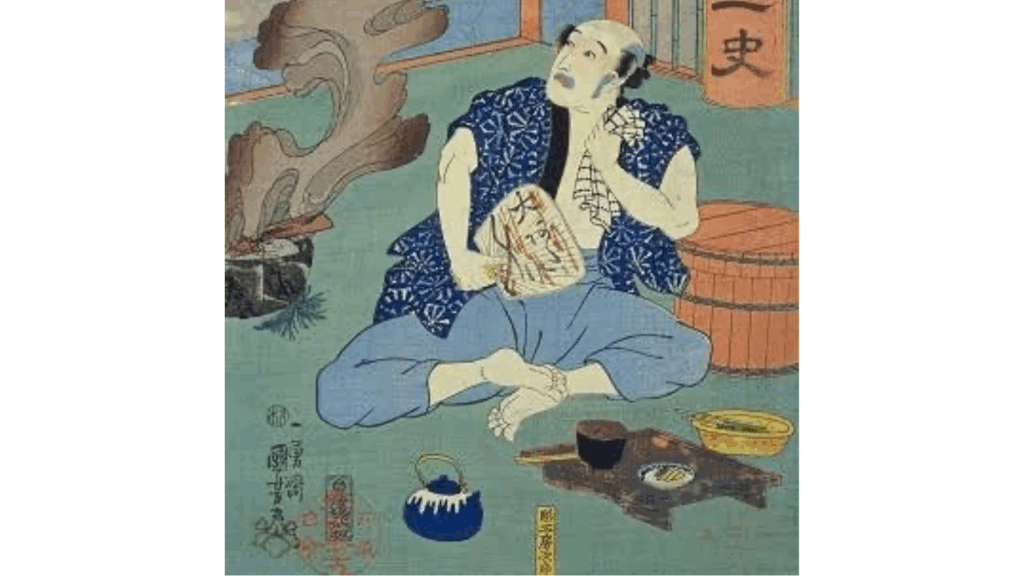
そんな江戸っ子の間では、いつしか「精米された白いご飯」を食べることが一種のステータスとされ、主食はほぼ白米だけという食事スタイルが定着していきました。1日5合食べる人もいたと言われています。
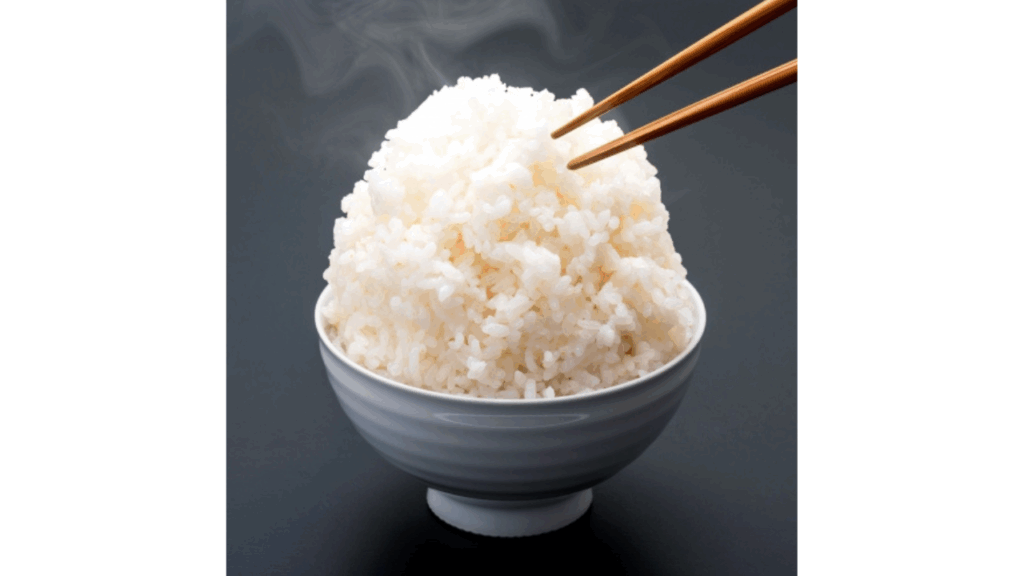
ところが、白米は精製過程でビタミンB1を多く含む「ぬか」が取り除かれてしまっていたため、長期間これしか食べていなかった彼らは体内のビタミンB1が不足し、その多くが脚気を発症してしまったのです。
ちなみに、地方では雑穀米や玄米を食べる習慣が続いていたため、江戸ほど脚気に悩まされることは少なかったそうです。
歴史に見る脚気の被害
実は江戸時代だけでなく、明治時代以降も脚気は深刻な問題でした。
特に、軍隊では白米中心の食事が奨励されたため、脚気患者が続出。日清戦争では、戦死者より脚気による死者の方が多かったという記録もあります。

この大問題に取り組んだのが、陸軍軍医の高木兼寛(たかきかねひろ)です。彼は、麦飯や洋食を取り入れた食事に変更することで劇的に脚気患者を減らし、原因が栄養にあることを突き止めました。
現代でも油断できない?
現代では国民の栄養状態の改善やビタミン剤の普及により、脚気はほとんど見られなくなりました。
昭和40年代頃まで小学校で行われていたハンマーで膝を叩く脚気の検査(膝蓋腱反射)もすでに廃止されています。
しかし、極端なダイエットや偏った食事を続けた場合、ビタミンB1不足に陥ることもあります。特に、アルコール中心の生活やインスタント食品ばかり食べる生活を送っている人は注意が必要です。
この記事のライター
physica編集部
楽しくて役に立つフィットネス情報をお届けしています。

