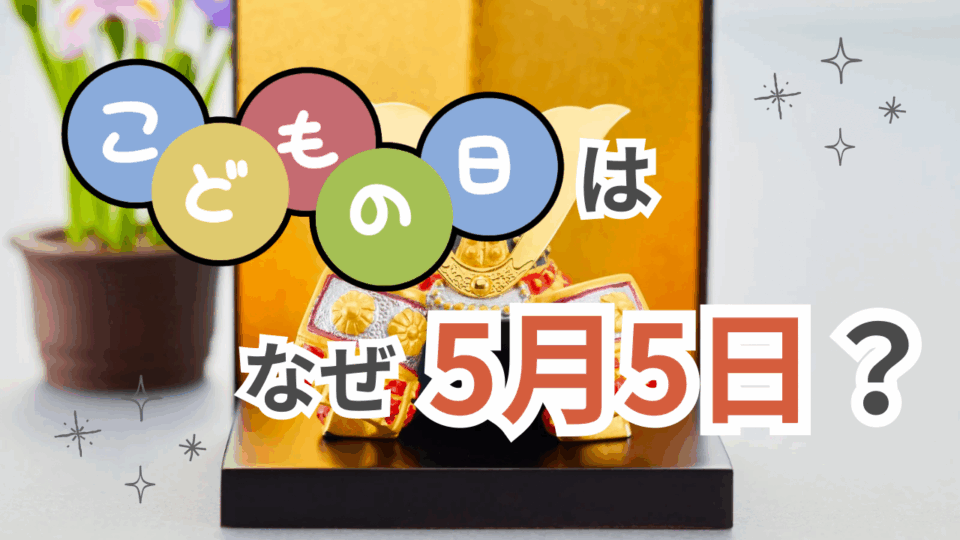
「こどもの日」はなぜ5月5日?端午の節句とこどもの健康 - physica
こんにちは、フィジカ編集部です。
ゴールデンウィークもそろそろ終盤。本日、5月5日は「こどもの日」そして「端午の節句」でもあります。
日にちが重なっているため混同されがちですが、端午の節句はもともと古代中国の厄除けの行事で、こどもの日とはまた(意味合いが)別のものになります。

端午の節句とこどもの日
中国での旧暦の5月は、気候の変化が激しく、病気が流行しやすい時期と考えられていました。そのため、この時期に人々が邪気を払い、無病息災を願う様々な行事を行っていたのが端午の節句の起源と言われています。
そしてこの行事は奈良時代の日本にも伝来し、広く庶民の間に広まっていくこととなります。
ここでポイントとなるのが「午(ご)」という音です。これは、数字の「五(ご)」と同じ音ですよね。この音のつながりから、日本では5月5日の行事として意識されるようになったと言われています。
その後、明治時代に入り、端午の節句は男の子の成長を祝う日として定着しましたが、1948年には「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」日として、男の子も女の子も分け隔てなく祝う「こどもの日」となりました。
5月の流行り病
そんな起源を持つ端午の節句ですが、実際5月というのは日本でも感染症が流行りやすい時期。特にこどもがかかりやすいのが以下のようなものです。
溶連菌感染症(A群溶血性レンサ球菌感染症)
ヒトメタニューモウイルス感染症
はしか、風疹、水疱瘡、おたふく風邪
いずれも感染には注意したい病気ですが、なかでも溶連菌感染症とヒトメタニューモウィルス感染症には有効なワクチンが存在しないため、手洗いやうがいなどの基本的な感染症対策が重要になります。
小さなお子さんを持つ方は、くれぐれもお気をつけ下さい。
無病息災。みなさんと全てのこどもにとって良い祝日になりますように!
この記事のライター
physica編集部
楽しくて役に立つフィットネス情報をお届けしています。

